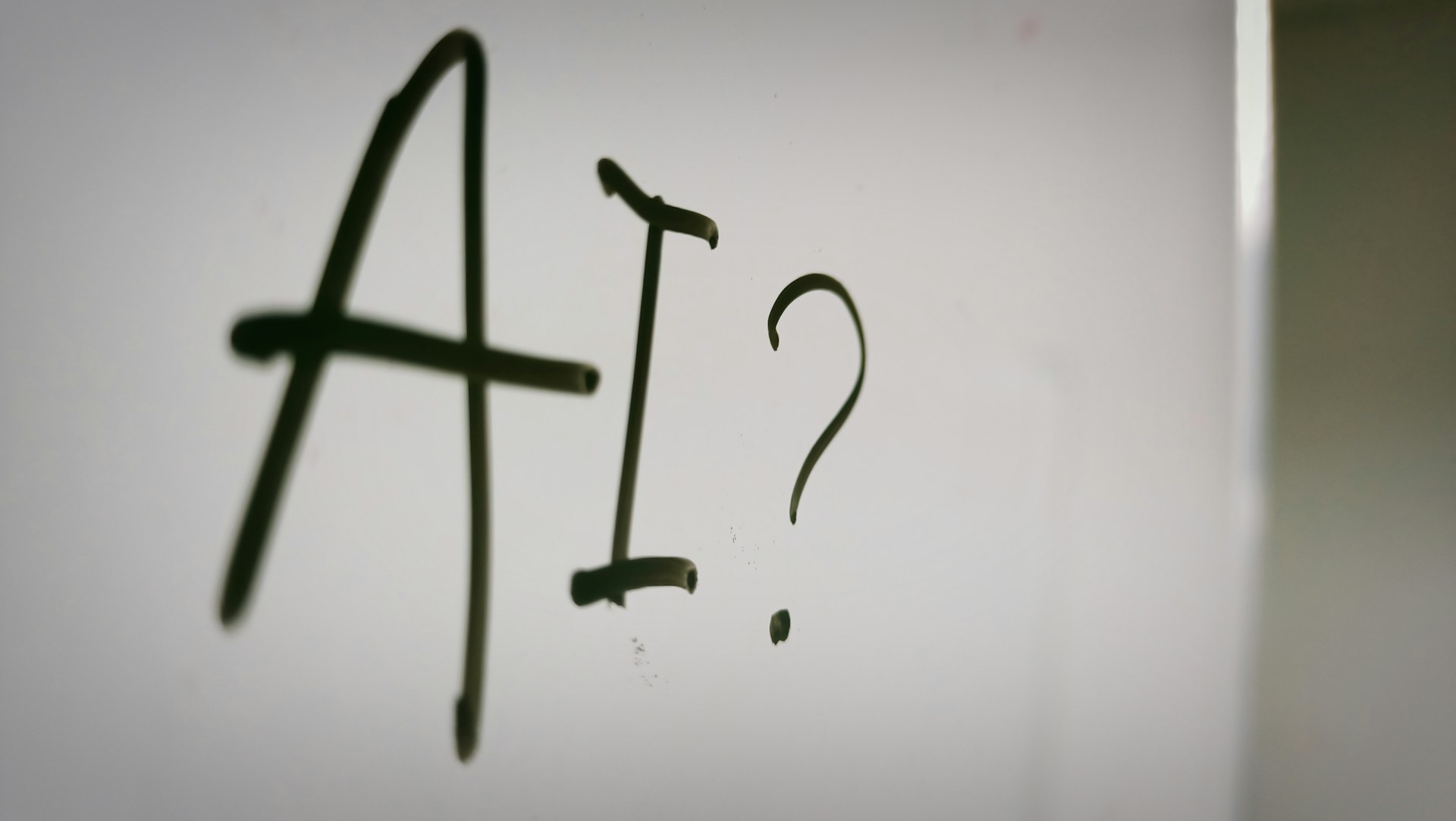
生成AIの基本概念とは
近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)やAI導入を検討する中で、特に注目を集めているのが「生成AI」です。日々ニュースやトレンドとして取り上げられ、人間の文章や画像、動画、音声などを自動生成する革新的な技術として、幅広い分野にインパクトを与えています。なぜ今そこまで話題なのかといえば、大量のデータを学習して高度な知能を発揮し、業務を自動化できるポテンシャルが大きいからです。既存のAIでは難しかった複雑な処理も、より自然な形で対応できるようになっています。例えば企業内のレポート作成や問い合わせ対応など、担当者の負荷が大きい業務を効率化する手段として、生成AIが期待されています。
企業がこの技術に熱視線を送る背景には、AI活用が単なる情報分析にとどまらず、新しい価値創出にもつながるという点が挙げられます。経営者やDX推進担当者は、生成AIを活用したサービスやプラットフォームによって、従来の仕組みを抜本的に変えたいと考えています。たとえば2025年には、生成AIの活用がブームから実用的な段階になり、日常の意思決定をサポートするツールとして「AIアシスタント」や「Copilot」が多数の企業で使われると予想されています(参考)。
一方で、過剰な期待が先行し、使いづらいと思われているケースもあります。実は、「プロンプトエンジニアリング」という言葉が広まったように、生成AIの成果は指示の出し方によって大きく変わります。適切な指示を与えれば人間の想像を超えるほど豊かなAI生成コンテンツが手に入り、そうでなければ精度を生かすのが難しいとされています。SHIFTという企業の事例でも、売上高を急伸させる過程で個人単位の高度な教育と生成AIの正しい使い方の推進が重なり、効果を上げたといいます(参考)。
ここでは、生成AIの解説に加え、どのようにビジネスで活用していけばよいのか、その基礎を押さえていきましょう。上手に取り入れれば、社内リソースの効率的な活用や業務時間の大幅削減につながる可能性があります。DX推進担当者や経営層にとっては見逃せない技術です。
AI生成ツールで変わる業務効率
AIを活用して社内問い合わせへの対応を自動化したり、文書作成やデータ集計をスピーディに行ったりするために注目されているのが、いわゆる「生成AIツール」です。これらのツールは、企業の膨大なFAQや社内ドキュメントを元に適切な回答を生成し、必要があれば担当者と連携して対応を進めます。例えばPKSHA Technologyは北陸電力で自動応答型のAIヘルプデスクを導入し、電話問い合わせの原則禁止まで踏み切った改革を実現しました。Microsoft Teams上での利用が進み、情報のやり取りを効率化しています(参考)。
また、ソニーグループでは約4万5000人の社員が生成AIを活用できるよう環境を整備し、毎月200万回以上という膨大な利用実績から5万時間分の業務時間を削減しているという報告があります(参考)。これは社内情報をクラウド上で一元的に扱い、複数の生成AIモデルを試せるハイブリッドなプラットフォームの構築を行った成果です。生成AIの本質は単なるコスト削減にとどまらず、社員それぞれの能動的な業務改善を後押しする点にあります。
こうした大企業の事例は、まさに「AI生成」を使いこなすことでどれだけ生産性が高まりうるかを示唆しています。中小規模の企業でも、自社データと連携する生成AIツールやクラウドサービスを導入しやすくなっているので、社内DXを加速したい場合には試してみる価値は十分にあるでしょう。日常的な問い合わせ対応から専門手続きまで、一連の業務フローを自動化し、社員の空き時間をより付加価値の高い仕事に向けることが可能になります。
生成AIプラットフォーム導入の現状
最近の動向を見ていると、生成AIを社内で広く活用するためには、オンプレミス(自社運用サーバ)とクラウドを組み合わせたハイブリッドなプラットフォームが重要だという声が多く聞かれます。NECでは、複雑に入り組んだ法規制対応業務を効率化するべく、生成AIを組み込んだ新たなサービスを開発し、実証実験を進めています(参考)。このような分野では、セキュリティやコンプライアンスが厳格に求められるため、パブリッククラウドだけでなく、安心して活用できる仕組みが必要です。
例えば「2025年の企業における生成AI活用」はすでに実用段階に入るともいわれ、あちこちで“AIアシスタントの普及”が目立ちます。質の高いデータと信頼できるプラットフォームの整備が不可欠であり、膨大なデータがクラウドやオンプレミス、さらにエッジデバイスの領域に分散している現場も少なくありません。そのため安全に連携できるシステム基盤が重要になります(参考)。
こうした潮流にともない、クラウド版の社内Wikiサービス「GROWI.cloud」も生成AI機能を強化し、文書やファイルの内容を読み取って要約や修正を支援する「エディターアシスタント」を提供しています(参考)。自社独自のルールや専門情報への対応が求められる場合でも、カスタムモデルの利用によって柔軟に学習やトレーニングが実施できるのです。さらに、ネットイヤーグループのように、外部の有識者や投資家を顧問として迎え、生成AI推進のためのノウハウとネットワークを積極的に取り込むケースも増えています(参考)。
具体的な業務自動化・事例
多くのコンサル企業やITベンダーが、生成AIの具体的な導入事例や効果的な使い方を発信していますが、特に最近注目されるのが組織の変革と生成AIを掛け合わせた取り組みです。日立製作所の矢野和男フェローは、長年のビッグデータ解析から得た知見をもとに「三角形の法則」を提唱し、幸福度と生産性を両立するような組織づくりと生成AIの可能性を結びつけています(参考)。このように、ただAIモデルを導入するだけでなく、チーム全体の意識改革や働き方の変革を同時に進めることが、成功への近道となっています。
さらに、「生成AIがもたらす組織変革と知的生産の未来」では、過去のデータ分析にとどまらず、テキストや画像、さらには人文科学的な見地まで幅広くAIが扱えるようになる話が語られています。またリフレーミング力を高めることで、新しい問いを立てられる組織へ進化することが重要だと指摘されています(参考)。
こうした事例を見ると、生成AIの導入は単なる業務自動化に終わらず、社内文化の醸成や働き方改革とも深く結びついていることがわかります。たとえば、教師データとして社内ナレッジを活用し、問い合わせや決裁プロセスを極限まで自動化するなど、様々な応用が考えられます。専門部署でなくとも、上長の承認フローやデータの更新作業をAIが代行し、人は新しいアイデアの発案やコミュニケーションに専念できるのです。
生成AIを活用した未来への展望
生成AIは、ビジネススキルと教育の常識を大きく変える可能性を秘めています。国際労働機関(ILO)によると、世界の雇用の約24%が、このような自動化技術の進化から影響を受けると予想されています。完全に人間の仕事が奪われるわけではないものの、職種によっては大きな変化が起きるでしょう(参考)。一方で新しい働き口や職務内容が生まれ、人材市場全体に再配置が進む可能性も高いです。
大学や小・中学校でも、生成AIをどう教育現場に取り入れるべきかが模索されています。東京大学メタバース工学部ジュニア講座では、教員や小中学生、さらに保護者までを対象にしたオンライン講座を開講し、「生成AIの基礎」や「画像、動画生成のリスクと可能性」などをわかりやすく解説しています(参考)(参考)(参考)(参考)。昨今は数千円の月額利用料で高性能な生成AIソフトウェアを扱える時代に突入しており、長期間かけないと身につかないとされていた専門技術を、一気に短縮して習得できる可能性があります(参考)。
こうした流れは企業にとっても大きなアドバンテージにつながるかもしれません。今後は、社員一人ひとりのスキルアップやAIリテラシーを加速するため、内製研修を充実させる動きが広がっていくでしょう。部署や立場を超えて生成AIが使える文化を築くことで、新規事業開発や商品企画のスピードアップに結びつけることができます。
カスタマイズAIがもたらすビジネス効果
生成AIの活用領域は、商品検索・顧客体験の向上から、自動応答型チャットボットを使った接客支援、さらにマーケティング分析まで多岐にわたります。例えばヤフーの運営する「Yahoo!ショッピング」では、β版としてAIによる商品検索サポート機能を一部ユーザー向けに公開し、質問や希望に合う商品を最適にレコメンドする仕組みを実装しました(参考)。
一方、このような生成AIが人間の嗜好や感情的なニーズにも対応できるようになると、新しいビジネスモデルが続々と登場します。例えば「理想の仮想彼女」を生成して提供するサービスが現れ、エンターテインメントやコミュニケーションの在り方そのものを変えるかもしれません(参考)。さらにマーケティングの内製化では、生成AIを使って広告クリエイティブや顧客データの分析を自社内で完結しやすくなりました。非効率や属人化を解消した例として「生成AIで進むマーケティングの内製化と成功の3つの法則」では、スキル標準化や共通言語の確立が欠かせないと提案されています(参考)。
さらに顧客理解を深める分野でも、生成AIが力を発揮します。広告代理店などが主催するオンラインセミナーを活用し、実際のマーケティング事例や消費者インサイトを分析する方法にフォーカスすることで、日々変化する市場動向を掴みやすくなります(参考)。こうした動きは、中小企業においても大きな差別化要因になるでしょう。バラバラだった自社データと生成AIを組み合わせることで、ニッチ市場へのアプローチや見込み客とのコミュニケーション改善など、多方面で効果が生まれます。
定着させるための教育と社内リテラシー
DXやAI導入を経験した企業の中には、PoC(概念実証)で止まってしまうケースが少なくありません。原因のひとつは、社内でのAIリテラシーが十分に育成されていないことです。株式会社地域新聞社は、独自の「ペルソナデータベース」を構築することで、生成AIと読者データを組み合わせた新しいマーケティングモデルに取り組んでいます(参考)。しかし、これを成功に導くためには、社員がAIに対して抱く漠然とした不安を取り除き、具体的にどう使うかを学ぶステップが必要です。
DX推進担当者や経営層は、部署ごとに異なる業務要件やセキュリティポリシーを踏まえながら、人材育成計画を工夫するとよいでしょう。例えば、自社事例だけでなく他社の先進事例を踏まえた研修や、外部専門家との連携、チーム間での情報共有などです。生成AIはツールとしての可能性が大きい一方、正確な指示やデータ確認、市場の動向把握など“人間が目利きをする”部分も非常に重要です。導入したAIを使いこなせる部門を増やし、社員の間でノウハウを共有すれば、試験的なPoCに留まらず実務に根づいた変革が期待できます。
最終的には、セキュリティとプライバシーを確保しながら自社に合った生成AIを取り入れ、現場が納得して使い続けられる文化を醸成することが鍵となるでしょう。必要に応じてパートナー企業やコンサルを活用し、自前開発と専門家の力を組み合わせるのも有用です。今後のビジネスや働き方を大きく左右する生成AIだからこそ、慎重かつ柔軟な対応が求められます。
監修者
安達裕哉(あだち ゆうや)
デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。
2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。
著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。
(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))
出典
- https://news.yahoo.co.jp/articles/c022f5a24e4a8f0a3da7b98e9d9204176a173ae5
- https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2506/30/news045.html
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000206.000022705.html
- https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/03251/062600004/
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000977.000078149.html
- https://japan.zdnet.com/article/35234786/
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144438.html
- https://bizzine.jp/article/detail/11769
- https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_tags/%E7%94%9F%E6%88%90AI%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%80%81%E3%82%AB%E3%82%AE%E3%81%AF%E4%B8%89%E8%A7%92%E5%BD%A2%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B?r=1
- https://www.foresight.ext.hitachi.co.jp/_amp/_ct/17774013
- https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00461/061300415/?i_cid=nbpnb_top_latest
- https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0104_01876.html
- https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0104_01874.html
- https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0104_01873.html
- https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0104_01877.html
- https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2025/07/ilo_02.html
- https://toyokeizai.net/articles/-/886595?display=b
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000048646.html
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000048646.html
- https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01194/00005/
- https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000087661.html
Photo:Nahrizul Kadri

