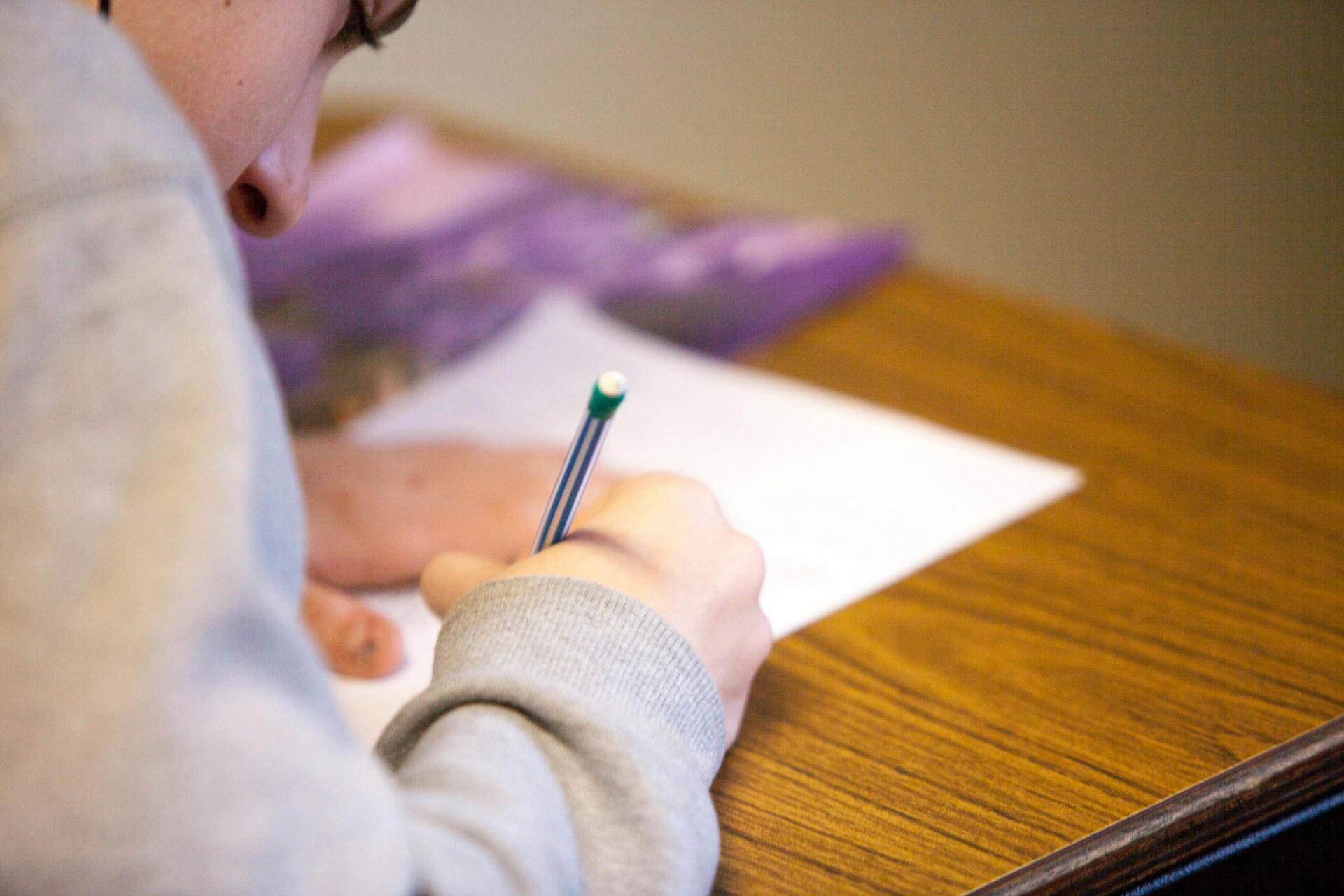
生成AIとカンニング問題の現状
近年、文章生成AIをはじめとするAI支援ツールへの注目が高まっています。企業の人材採用や大学入試のオンライン化が進む中、利便性の向上と同時に、不正行為、特にカンニングのリスクが顕在化しています。株式会社サーティファイの調査によると、2024年から2026年卒業予定の学生591名のうち、45.5%がオンライン就職試験で何らかのカンニングを行い、その中でも生成AIを使った不正が「替え玉受験」を上回る結果となりました(参考*1)。また、不正を行った学生の62.5%が内定を獲得しており、企業の採用の公平性や信頼性が問われています。エントリーシート(ES)作成でも、ChatGPTなどの生成AIを活用する学生が増加し、従来のSNSで流行した定型文の書き換えから、より多様な表現や自己PRが可能になっています(参考*2)。一方で、本人らしさが伝わりにくい、学習機会の損失といった課題も指摘されています。企業や教育機関は、こうした生成AIカンニング問題に対し、多面的な対策を検討しています。
急増するオンライン不正行為への対処と採用テスト
オンライン就職活動のWebテストにおけるカンニング行為は、企業の監視体制の強弱が受験者の心理に大きく影響しています。株式会社サーティファイの調査では、不正を行わなかった学生の73.5%が「不正の責任は企業側にもある」と回答し、62.3%が監視の甘い企業に不信感を抱いていることが明らかになりました(参考*3)。このような状況は、企業の評判や人材確保にも影響を及ぼしています。エンジニア採用向けの「Track Test」では、受験中のWeb行動を記録するアクションログ機能を導入し、コードの貼り付けや外部サイトの閲覧履歴などを可視化することで、不正行為の検出精度を高めています(参考*4)。技術的な対策と受験者への公正な説明が、今後の採用活動の信頼性向上に不可欠です。
不正防止技術の最新動向
不正行為を防ぐための生成AI対策技術も進化しています。株式会社サーティファイは、PCとスマートフォンの2つのカメラを同時に利用し、受験者の手元や背後を監視するオンライン試験システムの特許を取得しました(参考*5)。この技術は、従来の監視方法では発見しづらかった巧妙なカンニング行為を抑止し、入試や資格試験など重要な場面でのオンライン化を支えています。東北大学のFuture Global Leadershipプログラムでは、オンラインプラットフォーム「TOEP」を活用し、PCとスマホの併用による高精度な監視システムを導入しました。これにより、世界中の受験者が公平な環境で試験を受けられる体制が整っています(参考*6)。
大学のAI利用ガイドライン
高等教育機関でも、生成AI活用とカンニングリスクへの対応が進んでいます。大阪公立大学は、課題制作や研究活動での生成AIへの過度な依存を戒め、学びの意義を損なわないようガイドラインを整備しました。生成AIの出力をそのまま作品として提出することや、許可なく生成AIを使って解答や意見を提出することは、不正行為とみなされる場合があります(参考*7)。一方、大分県立芸術文化短期大学では、生成AIの利用を一律禁止せず、担当教員の指示に従う運用を行っています。個人情報の入力や著作権侵害リスク、生成AIの出力内容の正確性などにも注意が必要です(参考*8)。
国際的視点と学術的誠実性
海外の高等教育機関でも、生成AIツールの利用ルールが整備されています。ニューヨーク大学(NYU)では、教員が許可した場合に限り生成AIの利用が認められていますが、無断使用は学術的誠実性ポリシー違反となります(参考*9)。スタンフォード大学の研究では、生成AI導入後も不正行為の主な原因は過度な課題負担や時間不足であり、AIツールの普及が不正率を劇的に増加させていないことが示唆されています(参考*10)。ただし、AIツールの登場により教育現場の信頼関係や規定が複雑化する懸念もあります。
AI検出ツールの課題と留意点
生成AIによるカンニングを防ぐため、AI生成を判別する検出ツールが開発されています。しかし、スタンフォード大学の研究によると、英語を母語としない人の文章を誤ってAI生成と判定する事例が61%以上に上るなど、検出ツールの信頼性には課題があります(参考*11)。また、教育現場での導入には、誤判定による学生への心理的負担や学業上の不利益も懸念されています。AI検出ツールに頼りすぎず、学生との対話や文章内容の再確認など、多面的な評価が求められています(参考*12)。
教育とビジネスへの影響と今後の展望
画像生成AIや文章生成AIの普及により、就職活動や大学の講義、企業の業務効率化など、さまざまな現場でAI活用が進んでいます。対面環境の減少とともに、オンライン化が進む中で、業務効率や評価の公正性、創造性の正確な把握が課題となっています。最新の研究では、AIツール導入による不正率の劇的な増加は確認されていませんが、疑念や不信感が広がっている点が指摘されています(参考*13)。一部の学生は、課題や試験で生成AIを利用して負担を軽減しています(参考*14)。企業も顧客対応や文書処理の効率化を目指し、生成AI活用による競争力強化を模索しています。一方で、不正利用や学習機会の減少が長期的な人的資本の低下につながる懸念もあり、倫理や公正性を重視した運用設計が求められています。今後は、採用選考や学習支援の公平性を担保する技術や、AIと人間の役割分担を明確にする指針が重要となります。
監修者
安達裕哉(あだち ゆうや)
デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。
2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。
著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。
(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))
出典
- (*1) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 就活のWebテスト、45%が不正実行――生成AI悪用も横行
- (*2) 東洋経済オンライン – 「AIにES(履歴書)を書かせる就活生が急増」それを“けしからん”と言う人のほうが間違い…《AIに経歴を”加工”させる》学生が優秀であるワケ
- (*3) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 就活のWebテスト、監視の甘い企業に60%以上が不信感
- (*4) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – コーディングテスト「Track Test」、エンジニア採用試験中の不正行為やChatGPT等のAI利用の検出をサポートする「アクションログ」機能を搭載。
- (*5) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 【スマート入試】カンニング撲滅! サーティファイのオンライン試験システムが特許を取得しました
- (*6) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – スマート入試、東北大学FGLの公正なオンライン入試を支援
- (*7) 文学部・文学研究科 社会学教室 – 生成AIの利活用に関する学生向けガイドライン|文学部・文学研究科 社会学教室
- (*8) 大分県立芸術文化短期大学 | 芸術系・人文系をもつユニークな公立短大(芸術・文化系) – 生成AIのルール | キャンパスライフ
- (*9) Generative AI and Large Language Models (LLMs)
- (*10) Opinion: Is student use of generative AI cheating? The answer is complicated
- (*11) AI-Detectors Biased Against Non-Native English Writers
- (*12) Center for Innovative Teaching and Learning – Center for Innovative Teaching and Learning
- (*13) 阪南大学 公式サイト – ChatGPT等の生成AI利用に関するガイドライン|大学紹介|阪南大学
- (*14) Center for Teaching and Learning – Academic Dishonesty Using Generative AI – Center for Teaching and Learning
Photo:Ben Mullins

