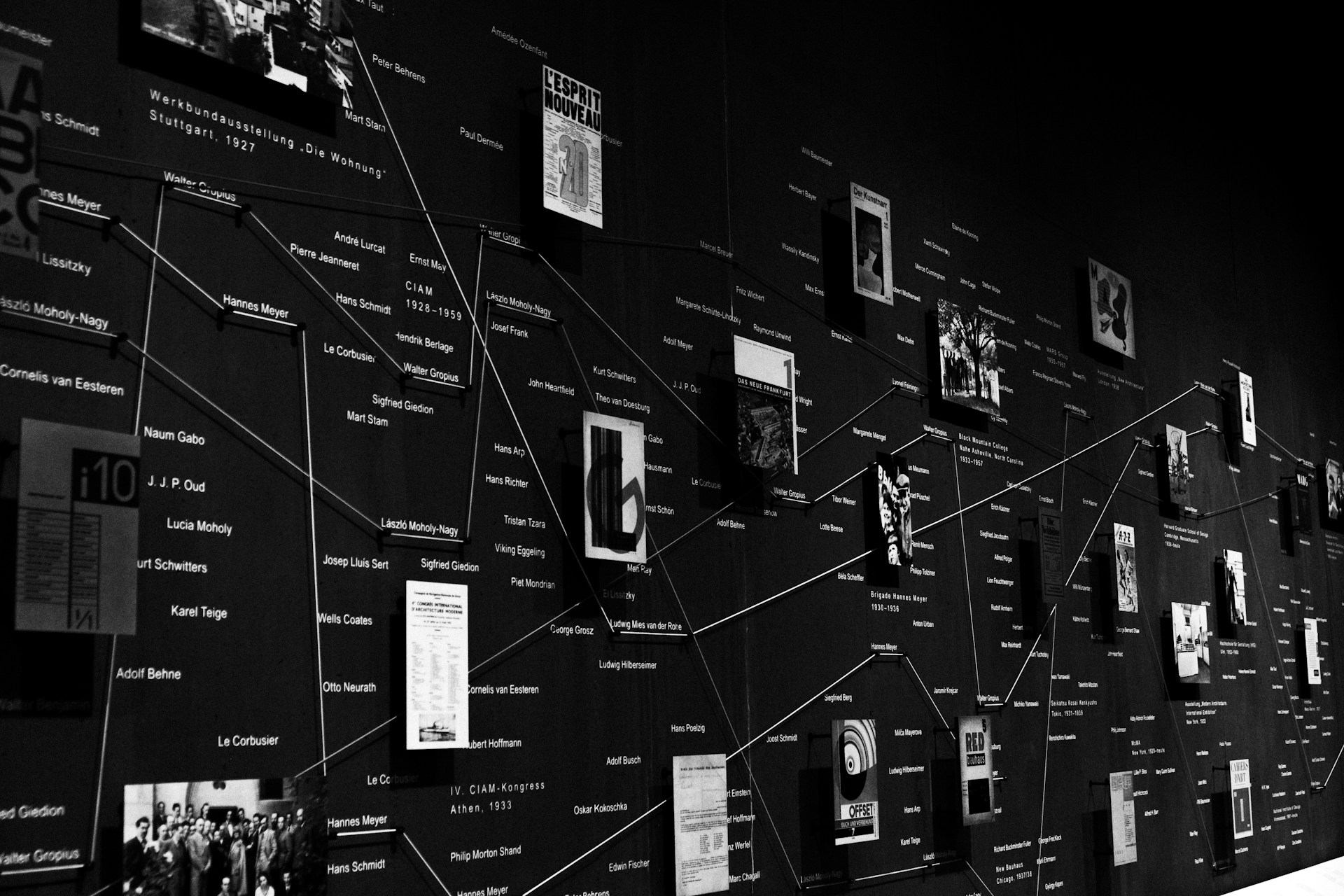
生成AIの歴史とその出発点を振り返る
生成AIの歴史は、人工知能(AI)の発展と密接に関係しています。1950年代、アラン・チューリングが「機械は人間のように考えられるか」という問いを提起し、1956年にはジョン・マッカーシーが「人工知能(AI)」という言葉を広めました。第1次AIブームでは自然言語処理を試みる手法も登場しましたが、当時は計算資源や大規模データが不足していたため、実用化には至りませんでした。1970年代から80年代には専門家システムが普及し、一時的にAI開発が進みましたが、データ整備や計算能力の限界から再び停滞期を迎えました(参考*1)。
その後、機械学習の台頭により、ビッグデータを活用した高精度な推定や分類が可能となり、人間の学習過程を数理モデル化する研究が活発化しました。特にディープラーニング(深層学習)と呼ばれる多層構造のニューラルネットワーク技術が登場し、画像認識や音声認識などで飛躍的な精度向上を実現しました(参考*2)。
こうした技術的進歩の土台の上に、文章や画像を自動生成する「生成AI」が誕生しました。生成AIは、企業の業務効率化や顧客対応など多様な分野で注目されており、導入担当者の関心も急速に高まっています。生成AIの進化を理解することで、現在および将来の活用可能性がより明確になります。
人工知能の変遷と生成AIの出現がもたらした意義
AIの進化を振り返ると、1950年代はアイデア段階でしたが、1960~70年代に研究資金が投入され、対話システムなどの実装が進みました。しかし、当時のコンピューターの計算能力は限られており、人間の意思決定を模倣するには不十分でした。1980年代にはエキスパートシステムが登場し、特定分野の知識をソフトウェア化する試みが行われましたが、設定作業や例外処理の負担が大きく、実運用には課題が残りました。
その後、機械学習の発展により、データを学習させる手法が拡充し、業務効率化や現場タスクとの親和性が高まりました。AIの応用は教育現場にも広がっています。株式会社Highstoが開発した歴史トレーディングカードゲーム「Hi!story」では、AI技術で制作したイラストを用い、子どもたちが遊びながら主体的に歴史を学べる仕組みを実現しています(参考*3)。また、株式会社みんがくと玉川大学濵田研究室が共同開発した「歴史人物シミュレーター」では、生成AIを活用して歴史上の人物と対話できる機能を提供し、生徒が疑問を深めながら学べる環境を整えています(参考*4)。
これらの事例は、生成AIが教育や娯楽の分野でも新たな可能性を切り拓いていることを示しています。
教育と研究の現場で問われる生成AIの是非
生成AIの導入は急速に進んでいますが、教育機関ではその利用に慎重な姿勢も見られます。たとえば、西ワシントン大学歴史学科では、学生の読解力や分析力を育成するため、教員の許可がない限り生成AIの使用を禁止しています(参考*5)。この方針の背景には、歴史研究においては資料調査や評論、批判的思考など人間の思考プロセスが重要であるという考えがあります。
また、他の大学の歴史学部でも、生成AIや大規模言語モデルの利用が学術的誠実性を損なう可能性があるとして禁止されています(参考*6)。これは、誤情報や均質化、盗用のリスクがあるためです。AI技術の導入は、実務と教育の両面で慎重な検討が求められており、知識の積み重ねだけでなく、問題意識や解釈力の育成も重視されています。
生成AIの正確さを見極めるための視点と学術連携
生成AIによる文章や画像の生成は多様な場面で活用されていますが、誤解を招く情報が含まれることもあります。出力内容をそのまま鵜呑みにせず、モデルの制作者や目的、引用元を確認する習慣が重要です(参考*7)。
学術分野では、生成AIと人文学研究を結び付ける取り組みも進んでいます。九州大学では、生成AIとデジタルヒューマニティーズをテーマとしたイベントが行われ、AI技術が一次資料の活用や新たな分析手法の提示に役立つ可能性が議論されています(参考*8)。
歴史分野では、データベース化された過去の出来事を解析し、新たなシナリオを生み出す試みも注目されています。こうした新領域の開発には、人間の批判的視点を保ちつつ、AIの利点を活用することが鍵となります。
ビジネス応用とクリエイティブ表現の拡散
生成AIは歴史研究だけでなく、ビジネスや芸術領域にも広がっています。ヤノベケンジ氏は、宇宙をモチーフにした芸術作品で生成AIを活用し、生命の誕生や文明の成り立ちを独自の視点で表現しています(参考*9)。AIによるイメージ生成は、クリエイターの発想を支援する新たな可能性を示しています。
ビジネス現場では、文書整理や顧客対応の自動化など、業務負担を軽減するための生成AI導入事例が増加しています。特に大企業ではクラウドプラットフォームを活用し、画像や文章の自動生成による接客や社内ドキュメント作成の効率化が進んでいます。日本国内でもDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、生成AIを活用したサービスが拡大しています。生成AIは大量のデータを瞬時に処理し、ニーズに応じた成果物を生み出すため、競合他社との差別化を図る選択肢として注目されています(参考*10)。
生成AIの進化と今後の展望
生成AIは、機械学習やディープラーニングの進化に支えられ、段階的に高度化してきました。過去の停滞期を乗り越え、革新的なAIアルゴリズムと演算資源の進歩が相まって、現在の生成AI革命が実現しています。今後は、学習データの品質管理やAI倫理への配慮が一層重要になると予想されます。大量のモデル訓練によるエネルギー消費や、ネット上の差別的発言を再学習するリスクに対しては、事前のチェック体制やAI人材育成が不可欠です。
企業のAI導入担当者にとっては、組織の教育やプロジェクト管理、セキュリティ対策を含めた包括的なアプローチが求められます。生成AIは単なる自動化ツールではなく、新しいビジネス手法やクリエイティブの可能性を切り開く存在です。今後は、より高精度な言語モデルや多模態(テキスト以外のデータを組み合わせて活用する仕組み)の活用が進み、歴史や文化的文脈の再解釈にも新たな機会が生まれるでしょう。教育、研究、ビジネスの現場でAI技術がパートナーとなる未来が期待されます。生成AIの歴史を学ぶことは、今後の企業活動や社会変革の礎を築くうえで不可欠です。
監修者
安達裕哉(あだち ゆうや)
デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。
2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。
著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。
(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))
出典
- (*1) Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア – AI(人工知能)の歴史|時系列でAIブームについてや今後の流れについて簡単にわかりやすく解説!|Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア
- (*2) AI Tools and Resources
- (*3) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 日本初「生成AI×歴史カードゲーム」株式会社Highsto法人化のお知らせ
- (*4) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – みんがく、旺文社のデータに基づき歴史上の人物と対話ができる生成AIアプリ「歴史人物シミュレーター Ver2」の実証実験モデル校の募集を開始 ~玉川大学濵田研究室との共同開発~
- (*5) Department of History Policy on the Use of Generative Artificial Intelligence in the Classroom
- (*6) Department of History Policy on Generative “AI” [Artificial Intelligence] – Bucknell History Department
- (*7) AI Tools and Resources
- (*8) シンポジウム「接続する人文学」〈科学史から見た生成AIとDH〉を開催します
- (*9) 瓜生通信 – 「宇宙猫」から始まる芸術の歴史とAI時代の創造力 ヤノベケンジ「宇宙猫の秘密の島」
- (*10) 公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO) – 【開催終了】技術移転セミナー「ChatGPT(生成AI)がもたらすイノベーション」(国際フロンティア産業メッセ2023 併催イベント)(2023.9.7開催) ‣ NIRO(公財)新産業創造研究機構
Photo:Moritz Kindler

