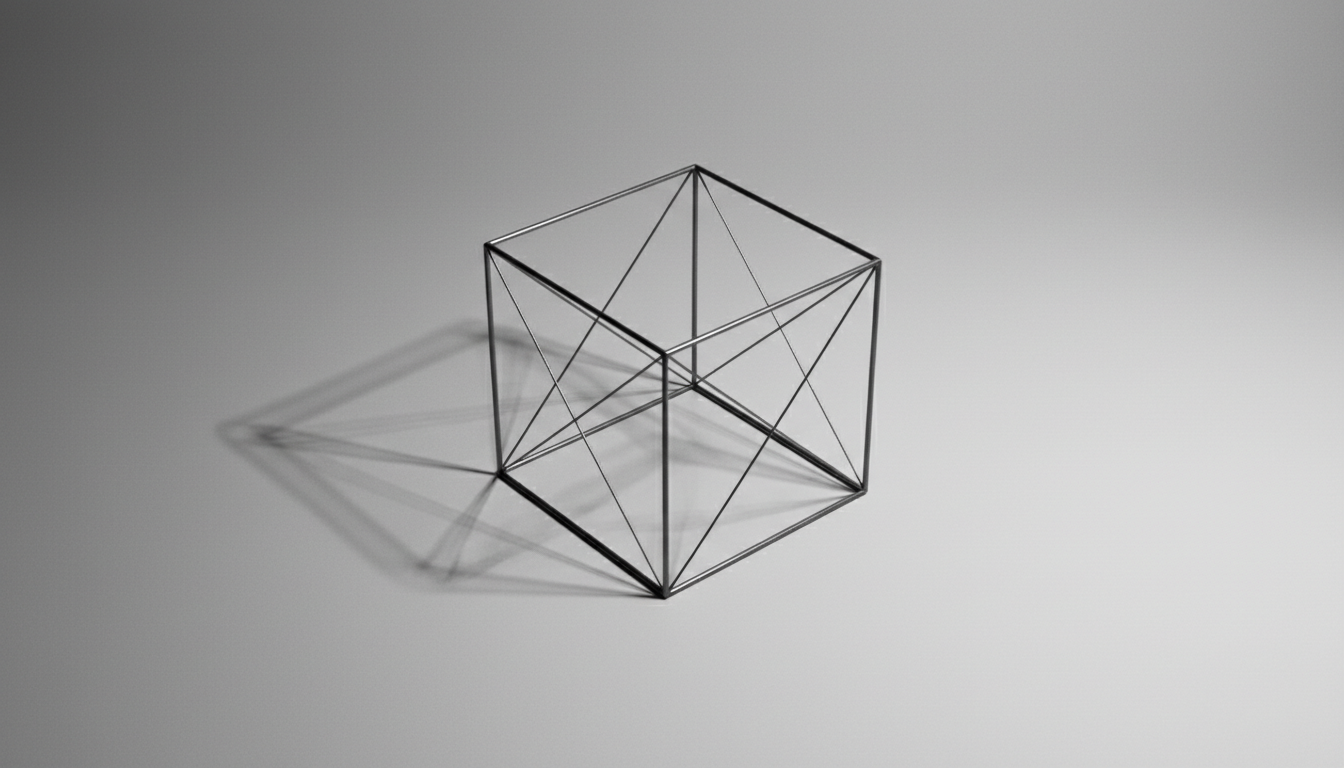
はじめに
近年、生成AIは画像や文章の制作だけでなく、3Dモデルの分野にも急速に広がっています。高度な演算技術を背景に、従来の想像を超えるクオリティのコンテンツを自動生成できる仕組みが注目されています。これにより、専門的なスキルがなくても多彩な立体表現を手軽に作成できるようになり、人の想像力をさらに広げる可能性が見えています。従来は手作業が中心だった3D制作プロセスの効率化が進み、映像やゲーム、建築設計など多岐にわたる分野で応用が進んでいます。
本記事では、生成AIと3Dモデルの連携がもたらす新たな展開について、技術的な仕組みから具体的な応用事例まで幅広く解説します。制作コストや時間の削減だけでなく、普段の作業フローへの影響や今後の発展性、課題についても考察します。
生成AIと3Dモデルの基礎
生成AIと3Dモデルの関係を理解するには、それぞれの基礎を押さえることが重要です。まずは生成AIがどのように学習・推論を行い、3Dモデルにどのような恩恵をもたらすのかを整理します。あわせて、3Dモデル制作の歴史や背景にも触れ、なぜ生成AIがこの領域で大きな注目を集めるようになったのかを解説します。
生成AIの特性
生成AIとは、ディープラーニング(深層学習)などのアルゴリズムを用いて、過去に学習した情報を基に新しいデータを自動生成する技術です。画像や文章だけでなく、物体の形状や質感など多様な情報を扱えるため、3Dモデルへの応用が急速に進んでいます。
総務省の資料によると、メタバースの市場規模は2022年に461億ドル、2030年には約5,078億ドルへ成長すると見込まれています(参照*1)。生成AIは、この巨大市場で創作・開発プロセスを効率化する原動力とされており、テキストによる指示だけで高度な3Dオブジェクトを形成できる可能性が広がっています。特にゲームやアプリ開発の初期段階では、迅速なプロトタイピングや多様なバリエーション生成に大きな利便性をもたらします。自動生成の普及により、これまで専門性が高かった3Dモデル制作がより身近なものとなり、クリエイティブな発想の幅も拡大しています。
また、画像を解析して新しい視点や物体の差異を補完する仕組みにより、細部まで高精度なモデルを出力できる点も注目されています。こうした高精度化の背景には、複雑な数理モデルの導入や、研究機関・企業による技術開発競争の活発化があります。
3Dモデル制作の背景
3Dモデル制作は、建築や製造、エンターテインメントなど幅広い分野を支えてきました。初期は手作業によるポリゴンの成形やテクスチャの貼り付けが主流で、時間と専門スキルが必要でした。ソフトウェアの進歩により作業効率は向上しましたが、高精細なモデルを多数制作するには依然として膨大なコストがかかるという課題が残っていました。
こうした中、株式会社Polyscapeが2024年6月に公開した短編ゲーム『みんなのMOZOO』では、生成AI技術を応用し、不思議な生命体MOZOOのモデルを言葉の指示だけで自由に変身させる仕組みが導入されました。プレイヤーはテキスト入力でキャラクターの外見や動きを切り替えられ、従来の手作業によるリアルタイム編集を大きく上回る効率化を実現しています(参照*2)。この事例は、3Dモデル制作に対する認識を一変させるきっかけとして高く評価されています。
3Dモデルと生成AIの連携技術
ここからは、生成AIによって3Dモデルがどのように生成・加工されているのか、技術的な観点から解説します。近年注目されている拡散モデル(Diffusionモデル)をはじめとする先進的な手法や、仕上げ段階におけるUVマッピングとテクスチャの役割について整理します。
Diffusionモデルの活用
Diffusionモデルは、ノイズを徐々に除去しながら高品質なデータを生成する確率的手法です。もともとは2D画像生成分野で発展しましたが、その考え方を3D領域に展開することで、立体物の形状や質感を細かく表現できるようになっています。Google Researchが発表したDreamFusionは、2Dで培われたノウハウを応用し、テキスト指示に従って多様な3Dオブジェクトを出力できることを実証しました。
さらに、MITの研究グループはScore Distillation(SDS)という手法に修正を加え、従来の拡散モデルが苦手としていたシャープな輪郭を持つ3D形状を高精度で生成する技術を開発しています(参照*3)。また、NVIDIAはMagic3Dというテキストベースの3Dモデル生成システムを公表し、DreamFusionと比較して解像度を約8倍、生成時間を約半分に短縮するなど、処理効率と品質の両立を実現しています(参照*4)。これらの技術は、携帯端末でも扱えるような軽量化の取り組みと合わせて注目されており、より多くの人が高品質な3Dモデルを生成できる環境が整いつつあります。
UVマッピングとテクスチャ
3Dモデルの見た目を魅力的に仕上げるには、表面に割り当てるテクスチャ設定が重要です。ポリゴンで形状を作成しただけでは、色や模様、反射率などの情報が十分に伝わりません。そこで必要となるのがUVマッピングという工程です。これは、3D空間の座標を2D平面に展開し、画像データがどの箇所に貼り付くかを管理する手法です(参照*5)。
生成AIを活用することで、モデルの形状だけでなくテクスチャのデザインも同時に作成できます。例えば、高解像度画像をベースに自動でUVマップを組み合わせ、異なる質感のバリエーションを短時間で用意することが可能です。これは、ゲームや映画で大量のオブジェクトを扱う際に特に効果的で、複雑な色味や細部まで正確に表現されたモデルを高速に生成できる手段となっています。
生成AIによる3Dモデルの実践事例
続いて、生成AIを活用した3Dモデル制作の具体的な事例を紹介します。近年はエンターテインメントからインフラ領域まで、幅広い場面で大規模な3Dデータが作成されています。ここでは、ゲームコンテンツとデジタルツインの2つに着目し、最新動向を解説します。
ゲームコンテンツへの活用
ゲーム業界では、キャラクターデザインやマップ構築を効率化する方法として生成AIの導入が進んでいます。特に、幅広いユーザー層にアピールする多彩なビジュアルが求められるオンラインゲームやスマートフォンアプリでは、開発速度と高品質の両立が課題でした。生成AIはこの点を大きく改善し、試作段階のコンセプトアートから最終的な3Dモデル作成までを一貫して高速化できる可能性を示しています。
2024年3月17日、米Roblox社はテキストプロンプトから直接3Dオブジェクトを生成するAI基盤「Cube 3D」を発表し、オープンソースとして公開しました(参照*6)。ユーザーが入力した単語や文章に応じてキャラクターや環境が形成されることで、モデリング工程の一部が大きく自動化されます。また、前述の『みんなのMOZOO』のように、プレイヤーがリアルタイムにデザインへ影響を与えられる仕組みも登場しており、コンテンツの更新頻度が高いゲームほど恩恵が大きいと考えられます。
デジタルツインの応用
デジタルツインは、現実世界と同じ構造や動きを仮想空間内で再現する技術です。都市計画や物流シミュレーション、災害対策など多様な分野で導入が進んでいます。こうしたシーンでは高度な3Dモデルが必要となるため、作業の大部分を自動化できる生成AIの価値が高まります。特に、大規模な建物配置や道路の複雑な構造を再現する際には、正確な形状と豊富なテクスチャが不可欠です。
国土交通省の取り組みでは、人工衛星の写真や3D都市モデルを学習させることで、高精度のデジタルツインを自動生成する仕組みが開発されています。例えば、屋上構造物や道路標識の設置位置まで自動で補完し、実際の街並みに近い3D空間を迅速に再現できるようになりました(参照*7)。こうした精緻化は、防災計画や都市景観の検証などにも活用されており、公共インフラや都市再生プロジェクトなど幅広い分野で今後の展開が期待されています。
生成AIと3Dモデル制作のメリット・課題
生成AIがもたらすメリットは大きい一方、実際の運用には考慮すべき課題も存在します。コストや効率面では明確な優位性が認められる一方で、クリエイティブな工程とのバランスや品質管理が重要なポイントとなります。ここでは費用対効果と品質管理の2つの観点から整理します。
コスト削減と効率向上
生成AIの導入により、多くの単純作業が自動化されるため、制作スケジュールの短縮や人件費の削減が期待できます。アドビは2024年のGame Developers Conferenceで、Adobe Substance 3DへFireflyを統合し、3Dテクスチャや背景画像の生成をさらに効率化する新機能を発表しました(参照*8)。これにより、ゲーム開発者や工業デザイナーは従来の煩雑な作業を省力化し、より付加価値の高いタスクに時間を割けるようになっています。
また、東京を拠点とするMetAIは、産業界全体のコンテンツ制作を効率化するため、AIを活用した4つの新サービスを発表しました。最大10万ポリゴンまでの高品質3Dモデルを短時間で生成し、UnityやBlenderなど業界標準フォーマットで提供する仕組みを構築しています(参照*9)。これにより、初期投資や人的リソースの負荷を抑えつつ、多様な要求に応じたクリエイティブが可能となっています。
クオリティ維持と最適化
一方で、生成AIを活用すればすべての作業が自動化できるわけではありません。自動生成されたモデルには、意図しない形状のゆがみやテクスチャの不自然な重なりが生じる場合があります。特に、リアリティを追求するゲームや映像、精密な寸法が要求される設計モデルでは、細かな修正が必要です。こうした品質面の調整には、専門知識を持つクリエイターの監修や、従来のツールを用いた手動での最終仕上げが依然として求められています。
また、既存データとの互換性やセキュリティ面での配慮も重要です。大規模プロジェクトでは多数のソフトウェアやプラットフォームが連携するため、モデル形式の違いや素材管理の手法が統一されていないケースもあります。さらに、AIの学習で使用されるデータや出力されたモデルの著作権など、法的なリスク要素も無視できません。これらを踏まえ、計画的な運用と品質管理が安定した成果物の提供には欠かせません。
おわりに
ここまで、生成AIを活用した3Dモデル制作の基礎から具体的な事例、メリットや課題までを解説しました。画像生成やテキスト生成で注目されてきた生成AIは、3Dの分野でも大きな成長を遂げています。制作時間の短縮や表現の幅の拡大など、多くの可能性を提示する一方で、品質管理や法的側面、クリエイターの役割といった課題も残されています。
技術は日々進化を続けており、今後もさらに多様な分野へ波及していくことが予想されます。各企業や研究機関が新しい手法やサービスを打ち出すことで、生成AIと3Dモデルの連携は一層洗練され、これまでにないビジネスチャンスやクリエイションスタイルが生まれるでしょう。こうした流れの中で、実務者だけでなく多くの人々が3D制作に気軽に取り組める未来が近づいています。
監修者
安達裕哉(あだち ゆうや)
デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。
2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。
著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。
(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))
参照
- (*1) 総務省|令和6年版 情報通信白書|仮想空間(メタバース・デジタルツイン)
- (*2) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 3D生成AIで自由に3Dモデル生成して遊べるスマホ・PC用無料パズルゲーム「みんなのMOZOO」が本日リリース!
- (*3) MIT News | Massachusetts Institute of Technology – A new way to create realistic 3D shapes using generative AI
- (*4) IT MAGAZINE | みんな読んでる「高校生向けIT情報メディア」 – 『IT MAGAZINE』は最新のIT情報を分かりやすく解説する「高校生向けITメディア」です。毎日3分読むだけでITマスターに。【OCA大阪デザイン&テクノロジー専門学校】 – IT MAGAZINE | みんな読んでる「高校生向けIT情報メディア」
- (*5) UVマッピング 3Dデモ
- (*6) ITmedia NEWS – Roblox、3Dオブジェクト生成AI「Cube 3D」を発表
- (*7) Plateau – 3D都市モデルを活用した高精度デジタルツインの構築
- (*8) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – アドビ、Adobe Firefly 生成AIをAdobe Substance 3D ワークフローに統合
- (*9) プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES – 制作時間を最大80%削減―MetAIが放つ革新的AI技術で3D・アニメ・音声・スタンプ制作が変わる

