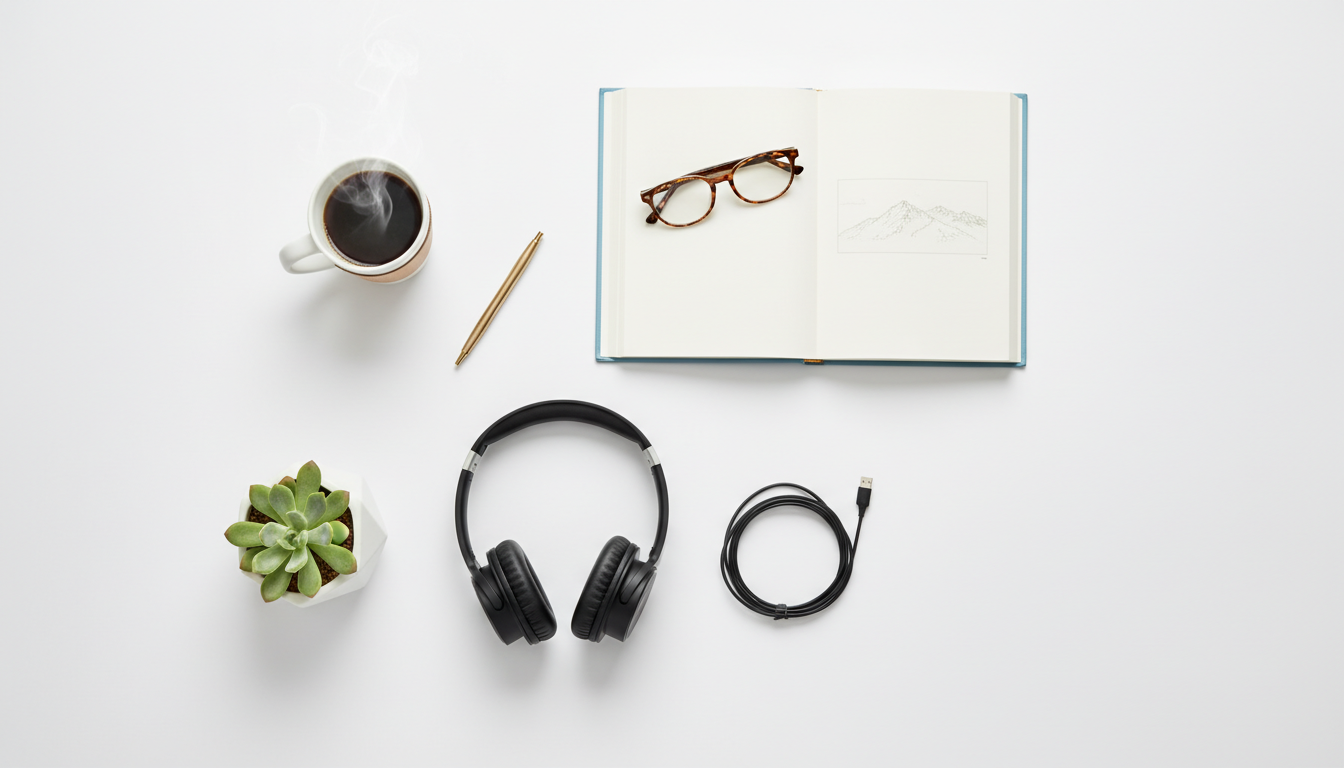
はじめに
画像生成AIは、テキストから多彩なビジュアルを自動生成できる技術として、近年大きな注目を集めています。デザインや広告、コンテンツ制作だけでなく、学術研究や個人の創作活動にも幅広く活用されており、企業のDX推進や業務効率化を目指す担当者にも関心が高まっています。この記事では、無料・有料それぞれの画像生成AIサービスの特徴を整理し、具体的な選び方や活用ポイント、トラブル回避策までを解説します。
はじめて画像生成AIを利用する方は、まず基本的な仕組みや選定基準を理解することが重要です。使いやすさや出力品質、セキュリティ、商用利用の可否など、目的や業務要件に合ったサービスを選ぶことで、期待する成果を得やすくなります。本記事では、実践的な指標や最新のトレンド、注意点も交えてご紹介します。
画像生成AIの基本と選び方
画像生成AIの概要
画像生成AIとは、テキストやキーワードを入力するだけで、AIが自動的に画像を生成する技術です。生成モデルと呼ばれるAIが、大量の画像データを学習し、ユーザーの指示に応じて最適なビジュアルを出力します。従来は専門的な知識や高価なソフトウェアが必要でしたが、現在はウェブサービスやアプリを通じて誰でも手軽に高品質な画像を作成できるようになりました。
初心者の方でも、操作が直感的なツールやオンライン教材、スクールが充実してきており、体系的に学ぶ環境が整っています。例えば、実務レベルを目指す方向けに11の画像生成AIスクールが紹介されている事例もあり(参照*1)、自分のレベルや目的に合わせて段階的にスキルを習得できます。
画像生成AIには、スマートフォン向けのアプリから企業向けの高度なソフトウェアまで多様なツールが存在します。用途や業務要件に応じて、最適なサービスを選ぶことがポイントです。
おすすめツールと選定基準
画像生成AIを選ぶ際は、操作性・出力品質・生成速度・コスト・商用利用の可否・セキュリティ・サポート体制など、複数の観点から比較することが重要です。特に、テキスト入力から画像生成までの操作が分かりやすいか、学習済みモデルの精度やバリエーションが豊富かどうかは、業務効率や成果物の品質に直結します。
複数のツールを比較する際は、実際にサンプル入力を試してみて、画風や画質、生成速度、編集機能の有無などをチェックしましょう。費用面では、無料プランは回数や機能に制限があることが多く、有料プランでは高解像度出力や商用利用ライセンス、追加編集機能などが提供されます。自社の利用目的や業務要件を明確にし、必要十分なプランを選ぶことがポイントです。
また、ある資料では画像生成AIのおすすめや使い勝手を深掘りした7つのアプリが紹介されており(参照*2)、用途や目的に応じて最適なツールを選ぶことが基本となります。
無料で始める画像生成AI
メリットと注意点
無料で画像生成AIを利用する最大のメリットは、初期投資なしで手軽にアウトプットを試せる点です。学生の研究発表や個人の創作活動、企業のPoC(概念実証)段階でも、コストをかけずに複数サービスを比較検討できます。
一方で、無料プランには生成回数や解像度、利用可能なスタイルや機能に制限がある場合が多く、商用利用が不可なケースも少なくありません。利用規約を確認せずに画像を業務やビジネスに転用すると、著作権やライセンス違反のリスクが生じるため注意が必要です。
無料プランを活用する際は、権利関係やライセンス内容を必ず確認し、業務利用や商用利用を想定する場合は有料プランや商用ライセンスの取得を検討しましょう。
代表的な無料ツール
代表的な無料画像生成AIツールとしては、Bing Image CreatorやFreepikなどが挙げられます。Bing Image CreatorはMicrosoftが提供し、DALL-E2を活用してブラウザ上で一度に4枚の画像を生成できます(参照*3)。直感的な操作で多様な作風を比較できるため、初心者の学習やPoC用途にも適しています。ただし、現時点では商用利用は不可となっており、業務利用の場合は注意が必要です。
Freepikは1日あたり40枚の無料クレジットが付与され、ダウンロード時に透かしが入らない点が特長です(参照*4)。素材の豊富さと利便性から、個人クリエイターやセミプロの表現活動にも活用されています。ただし、特定の要件を満たさない場合は有料プランへの移行が必要となるケースがあるため、利用規約の確認が不可欠です。
有料プランでのこだわり活用
プロ向け機能と料金比較
有料プランを選択すると、高解像度画像や高度な編集機能、カスタムモデルの利用など、プロフェッショナル向けの機能が充実します。広告や出版、商品パッケージのデザインなど、品質や独自性が求められる現場では有料版の導入が効果的です。
例えば、Midjourneyは独自性の高い美しい作風と表現力で評価されており、継続的な機能アップデートも行われています(参照*5)。有料サービスのため月額制やクレジット制など料金体系が異なり、月額20ドル程度のプランから、チーム向けや高度なサポートを含む上位プランまで幅広く用意されています(参照*6)。
有料プランでは商用利用ライセンスが明確に付与されるケースが多く、権利関係のリスクを抑えやすい点もメリットです。ビジネス利用では、実際の生産効率やコストとのバランスを検討し、必要な機能やサポート範囲を明確にしたうえで導入を進めることが重要です。
活用シーンとアドバイス
有料プランの活用シーンとしては、企業の広告制作や商品パッケージデザイン、ブランドイメージの構築などが挙げられます。精緻なニュアンスや独自性の高いビジュアルを求める場合、カスタマイズ機能やスタイル指定が充実した有料ツールが有効です。
例えば、ChatGPT Plusの画像生成機能を活用することで、対話形式でのプロンプト調整やワークフローの効率化が可能となり、多くのクリエイターや業務担当者の負担軽減につながります(参照*6)。
有料契約前には、無料トライアルやサンプル生成を必ず試し、実際の生成画像が業務要件や用途に合致するかを確認しましょう。職種や組織規模によって最適なプランは異なるため、現場の要件整理や追加費用の有無、サポート体制も含めて比較検討することがポイントです。
おすすめ画像生成AIの比較
性能・特徴の一覧
ここでは、おすすめの画像生成AIを主要な観点で比較します。一般的な評価基準は、美術的な表現力・生成速度・操作性・商用利用の可否・料金体系・セキュリティ・カスタマイズ性などです。
ある資料では、Stable Diffusion、Canva AI、Midjourney、Flux、Ideogram、Adobe Firefly、Copilot、Fotorの8つが主要サービスとして挙げられています(参照*7)。Stable Diffusionはオープンソースモデルでコミュニティ主導の進化が特徴、Canva AIはデザインツールとしての統合性と初心者でも扱いやすい操作性が魅力です。Midjourneyは芸術性の高い表現力で評価され、デフォルトでは生成画像が公開される仕組みのため企業利用時は注意が必要です(参照*8)。FluxやIdeogramは新しい表現技術を積極的に取り入れており、Adobe Fireflyは大手ソフトウェア企業の信頼性と編集ツールとの連携が強みです。CopilotやFotorは操作性やテンプレートの豊富さで人気を集めています。
活用事例と使い勝手
実際の活用事例としては、マーケティング資料やSNSコンテンツ、プレゼン資料のビジュアル作成などが挙げられます。Midjourneyを使えば独創的なアート風イラストが手軽に得られ、ブランドイメージ重視の分野に適しています。Canva AIやFotorのようにテンプレートや編集機能が充実したツールは、短時間で大量の画像を作成する業務に向いています。
使い勝手を比較する際は、インターフェイスの分かりやすさや出力画像のライセンス、カスタマイズ性、API連携の有無なども確認しましょう。独自のブランド要素を反映できるかどうかも、業務利用では大きな差となります。複数サービスを実際に試し、生成品質や運用コスト、ワークフローへの適合性を総合的に評価することが重要です。
トラブルリスクと著作権対応
気をつけたいリスク要因
画像生成AIの利用にあたっては、技術的な精度だけでなく、セキュリティや倫理面への配慮も不可欠です。例えば、機密情報や個人情報をプロンプトに入力した場合、データが外部に漏洩するリスクがあります。特にビジネス用途では、社外秘の情報や顧客データが画像生成に紐づく恐れがあるため、慎重な運用が求められます。
また、AIが学習したデータセットに偏りがある場合、差別的な表現や不適切なイメージが生成されることもあります。さらに、生成画像の著作権が不明瞭なまま第三者に提供されたり、営利目的で使用されるケースも問題視されています。
こうしたリスクに対応するため、近年は安全性や倫理への配慮を重視したサービスも登場しています。例えば、Claudeは日本語の自然な文章生成と安全性への配慮が特徴であり、利用者のリスク軽減に寄与しています(参照*9)。国内外で法的側面への関心も高まっており、ガイドラインや社内規定の整備が進められています。
正しい著作権・法的配慮
画像生成AIで生成した画像は、従来のインターネット素材とは異なり、著作権やライセンスの取り扱いに注意が必要です。特に商用利用の場合は、各サービスの利用規約やライセンス条件を厳守することが重要です。
専門家やユーザーの実例を集めた調査では、契約書がないまま制作物を公開し、後から権利関係でトラブルとなったケースも報告されています(参照*10)。海外サービスを利用する場合は、現地の法律が適用されることもあるため、国際的な著作権ルールにも注意しましょう。
国内外問わず、利用ガイドラインやプライバシーポリシーを事前に確認し、不明点があれば専門家へ相談することが推奨されます。リスクを正しく理解し、法的配慮を徹底することで、安心して表現活動や業務活用が可能になります。
おわりに
画像生成AIは、多様なビジュアルを手軽に取得できる点で、企業や個人に新たな表現の可能性をもたらしています。無料・有料サービスの選択は目的や予算、業務要件によって異なりますが、活用シーンやリスクを明確にし、最適なサービスを選ぶことが成果につながります。
本記事では、基礎知識からツールの特徴・比較、注意点まで幅広く解説しました。実際に複数サービスを使い比べ、自社やチームのニーズに合ったスタイルを見つけることで、より豊かなイメージ表現や業務効率化が実現できます。進化を続ける画像生成AIの活用を通じて、新たな発想やビジネスチャンスを切り拓くことが期待されます。
監修者
安達裕哉(あだち ゆうや)
デロイト トーマツ コンサルティングにて品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事しその後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのち2013年5月にwebマーケティング、コンテンツ制作を行う「ティネクト株式会社」を設立。ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。
2023年7月に生成AIコンサルティング、およびAIメディア運営を行う「ワークワンダース株式会社」を設立。ICJ2号ファンドによる調達を実施(1.3億円)。
著書「頭のいい人が話す前に考えていること」 が、82万部(2025年3月時点)を売り上げる。
(“2023年・2024年上半期に日本で一番売れたビジネス書”(トーハン調べ/日販調べ))
参照
- (*1) 一般社団法人クラウドワーカーリスキリング協会 – 画像生成AIスクールおすすめ11選!選ぶポイントやスクール利用がおすすめな理由を解説
- (*2) 【無料】AIイラスト生成 最新おすすめアプリ7選【2025年最新版】
- (*3) Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア – イラスト・画像生成AIサービスのおすすめ7選|スマホアプリ・仕組み・将来性についても解説|Generative AI Media │ 生成AIに特化した専門メディア
- (*4) UX Magazine – I Tested 7 Free AI Image Generators. This One’s My Pick
- (*5) note(ノート) – AI画像を"無料"で作りたい人に、おすすめの生成AIツールをご紹介。|AI FREAK
- (*6) CNET – Best AI Image Generators of 2025
- (*7) AIの情報インフラを構築し、日本のAI推進を加速 – 画像生成AIでイラスト作成!おすすめ8選や選び方、コツを解説|SHIFT AI TIMES
- (*8) The 8 best AI image generators in 2026
- (*9) 【2025】生成AIおすすめアプリ10選!比較ポイントや注意点も紹介
- (*10) Yahoo!ニュース – 【生成AI】使いこなしているLEE100人隊に、おすすめの活用法を聞いてみました!なにを使ってる?どんなルールがある?(LEE)

